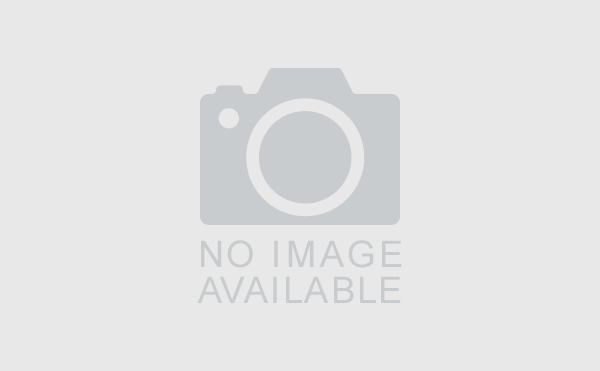企業理念とコンセプトの交差点で、今年の「物語」を描く
年が明けると、僕の頭の中に自然と浮かぶのは「今年の物語をどう紡ぐか」という問いだ。僕がコンサルしている飲食店では、企業理念を核にしながら、その周囲を柔軟なコンセプトが包み込む。そのコンセプトは不変のものではなく、むしろ消費期限があるものだと僕は思っている。
食べ物に賞味期限があるのと同じように、飲食店のコンセプトにも寿命がある。どれほど美しい理念であっても、その周囲を取り巻く社会の風景が変われば、その表現の仕方もまた変わらざるを得ない。今年の始まりに、まず取り組むべきはその設計図を見直すことだ。
理念は「北極星」、コンセプトは「風の方向」
企業理念は変わらない。それは夜空の北極星のようなもので、常にそこにあり、従業員や顧客の道しるべとなるものだ。しかし、コンセプトというのはその時々の風向きを読む行為に似ている。追い風を捕まえるのか、逆風に立ち向かうのか。その選択肢は無数に広がっている。
たとえば、「地産地消」という理念がある飲食店を考えてみよう。これをどう解釈し、どう表現するかは、時代や地域によって異なる。今年であれば、「地域との共創」という文脈が目を引く。地元の農家とともに商品開発を行い、その過程を顧客に公開するような取り組みが考えられる。
企業理念とコンセプト、その物語性について
企業理念とコンセプト。この二つの言葉を前にすると、僕はなんとなく、夜の浜辺を思い浮かべる。理念は砂浜に立つ灯台のようなものだ。一度その場所に立てば、どんなに暗い夜でも、その灯りを頼りに自分の位置を確認することができる。コンセプトは、それに対してもっと移ろいやすい波のようなものだろう。その時々の風や潮流によって形を変えるが、いつでも砂浜を撫でるという目的を忘れることはない。
理念は「存在の理由」
飲食店における企業理念は、その存在を支える土台だ。その店が、なぜそこにあり、何のために食事を提供するのかを語るもの。たとえば、「地域の人々をつなぐ」「健康的な食文化を広める」「食を通じて小さな幸せを届ける」。そんなフレーズが企業理念の姿をまとっていることが多い。
理念というものは、直接的に触れることができないものだ。僕たちは日々の生活の中で「地域のつながりを感じたい」とか「健康でありたい」といった欲求を抱いているが、その背景にある理念そのものを意識することは少ない。しかし、それはいつもそこにあり、その存在が確かであるからこそ、顧客は安心して店を訪れる。灯台がそこにあるだけで船乗りが安心するのと同じだ。
コンセプトは「今の語り口」
一方で、コンセプトはもっと生々しく、もっと触覚的だ。それは理念をどうやって具体的に伝えるかという「表現」の部分にあたる。コンセプトは形を持ち、色をまとい、目に見えるものであるべきだ。そしてその形や色は時代や場所、文化によって変わる。
たとえば、同じ「地域のつながり」という理念を掲げた飲食店でも、一つの時代には「地元の農産物を使った手作り料理」という形を取り、別の時代には「地元の人々と一緒に作るイベント型レストラン」という形を取る。つまり、コンセプトには寿命がある。いつかは古びてしまい、その役割を終える。だからこそ、定期的に更新される必要があるのだ。
コンセプトは理念の語り口を変える役目を持っている。どんなに素晴らしい物語でも、語り口が時代に合っていなければ、その魅力は伝わらないだろう。だから、コンセプトは時代に耳を傾け、今という波に寄り添いながら形を変える。それは少し気まぐれな恋人のようでもあり、真摯な案内人のようでもある。
二つのバランスを考えること
理念とコンセプトのバランスを考えることは、浜辺に立ち、灯台と波の関係を眺めるような行為だ。灯台がなければ波はどこに向かうべきかを見失うだろうし、波がなければ灯台はただ孤独に立ち尽くすだけだ。両者が共に存在していることで、浜辺の物語は完成する。
理念は変わらない。ただし、それをどう伝えるかを考え続けることが飲食店の仕事だと僕は思っている。そこには「物語性」が必要だ。理念という灯台が照らす光の先に、どんな未来があるのか。そのビジョンを具体的に描き、それをお客様や従業員と共有する。これがコンセプトの仕事だ。
こんな感じで、今年のコンセプトが決まる。あとはコンセプトに沿って従業員一同が行動できなければならない。
だからコンセプトは「みんなが行動しやすいワード」であることもポイントになる。
もしあなたが飲食店を経営しているなら、一度、こう考えてみるといい。今年、その灯台の光をどんな色の波で表現するのか、と。波の形や色は時代によって変わるが、灯台が照らす光が誠実であり続ける限り、その物語はきっと人々の心に届くだろう。